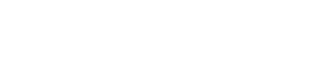会社設立の流れ
会社の種類としては、合同会社や合資会社、合名会社などもありますが、今日設立されている会社形態のほとんどは株式会社です。
会社法上、株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2つがあります。
発起設立とは、設立に際して発行される株式の全部を発起人が引き受けて設立する方法です。一方、募集設立とは、設立に際して発行される株式の一部を発起人が引き受け、残りの部分につき一般の株主を募集して設立する方法です。
実務上多く用いられるのは発起設立であるので、以下の会社設立の流れは発起設立を例として紹介します。
株式会社の設立を発起設立の方法で行う場合、発起人(会社設立を行う者)は次のようなスケジュールで進めていくことになります。
①発起人が会社の設立を決める
②会社の基本事項を決定する
決めることとしては、事業内容や、会社名、本店所在地などです。
③発起人等は印鑑登録をする
定款の認証(⑤)、設立登記(⑧)等の設立手続きの過程において、発起人や取締役となる者は実印が必要となるので、実印登録を行っていないならば、住民登録をしている市区町村役場で印鑑登録の手続きを行う必要があります。
④会社の印鑑を作成する
用意する印鑑としては、代表者印(会社の代表者が使用する印鑑)、社印(社名のみを彫った印鑑)、銀行印(銀行口座開設の際に届け出る印鑑)があります。
⑤定款を作成し、公証人の認証を受ける
定款とは、会社の組織・運営に関する根本規則です。作成した定款は、本店所在地を管轄する法務局等の公証人の認証を受けることによって初めて効力を生じます。
⑥出資金払込口座を開設して、出資金を払い込む
発起人は、会社設立後に株主になりますが、設立登記を行う前に、その引き受けた株式の発行価額の全額を払い込む必要があります。そして、発起人により払い込まれた株式の発行価額が、原則として株式会社の資本金となります。
⑦最初の取締役等を決める
最初の取締役(「設立時取締役」という)等を選任します。選任された設立時取締役と設立時監査役は、株式の払い込みが完了しているか等の調査を行います。
⑧設立登記の申請を行う
本店所在地を管轄する登記所(登記事務をつかさどる法務局等)に設立登記をすることによって、法的に株式会社が成立します。
⑨各官公署への届出を行う
事業を開始する前に、各種許認可等を取得し、また社会保険(健康保険、厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災保険)などの加入手続きを行います。
濱島久資税理士事務所では、法人・個人問わず、会計・税金に関わる業務・手続きを親身になってサポート致します。
東京中央区を拠点に、創業融資に関するご相談や、定款作成の代行に関するご相談、法人選択に関するご相談などにお応えし、会社設立にかかる費用・時間のご負担を軽減いたします。
会社設立・開業でお悩みの際は、当事務所までご連絡下さい。